「賞味期限って過ぎても食べられるって聞くけど…実際のところどうなの?」
食品の品質管理の仕事をしていると、よく聞かれるこの質問。そして意外と、誤解されていることも多いです。
今回は、「賞味期限」や「消費期限」の違いから、開封後の扱い、保存の注意点まで、消費者のリアルな疑問に寄り添う形でお話しします。
賞味期限と消費期限、どう違う?
まず大前提として、
- 消費期限:この日を過ぎると「安全性」に問題が出る可能性がある食品(例:お弁当、サンドイッチなど)
- 賞味期限:この日までに食べれば「おいしさ」が保たれる食品(例:スナック菓子、レトルト食品、インスタント麺など)
つまり、賞味期限は「過ぎたらすぐに食べられなくなる」わけではありません。
実際のところ、どこまで食べられるの?
よくあるのが「賞味期限が1週間過ぎたお菓子、食べていい?」という話。
基本的には、未開封で、表示どおりの保存方法が守られていれば、多少過ぎてもすぐに傷むわけではありません。実際、メーカーが賞味期限を設定する際には安全係数をかけている場合も多いです。
安全係数とは、商品が安全に食べられる期限から、どの程度余裕を持たせて期限を設定するかの基準。
メーカーでは、官能試験(味・見た目・香りなどの評価)や微生物試験、理化学試験などを行い、合理的・科学的な裏付けのもとで安全に食べられる期限を決めています。
この安全に食べられる期限が100日後だとすると、安全係数が0.8の場合、100日×0.8=80日後の賞味期限が設定されるわけです。
※安全係数は近年のフードロス削減の一環で「限りなく1に近づけることが望ましい」とのガイドラインが消費者庁から出されています。
どれくらい過ぎたら危険なのか、教えて!
これは食品によってまったく異なるため、一概に「これくらいなら大丈夫」とは言えません。
たとえば、缶詰のようにもともとの期限が年単位の食品と、牛乳のように数日単位の食品とでは、1週間過ぎた場合のリスクはまったく違います。
ポイントは、「もともとどれくらい日持ちする食品なのか」「常温保存か冷蔵保存か」などを確認し、判断の材料にすることです。
また、見た目・におい・食感・味などに違和感があれば、迷わず廃棄してください。
五感によるチェックも大切です。
切っても切れない関係、賞味期限と保存方法
食品表示には、「賞味(消費)期限」のほかに「保存方法」の記載もあります。
例えば「10℃以下で保存」「直射日光・高温多湿を避け保存」など。
この保存方法を守って初めて、期限が有効になります。たとえば、冷蔵品を常温で保存してしまった場合などは、もとの期限は意味をなさなくなると考えましょう。
また、「保存方法」も「賞味(消費)期限」と同様、未開封の状態を前提としています。
「常温保存可」と書かれていても、開封後は冷蔵が推奨される食品も多いです。開封後の保存方法は、一括表示の枠外などに書かれていることが多いので、そちらも忘れず確認しましょう。
開封したら、賞味期限は無関係?
はい。開封した時点で、賞味期限は無効になります。基本は「できるだけ早く食べる」が原則です。
とはいえ、調味料や瓶詰め、ジャムなどすぐに使い切れない食品もたくさんありますよね。
最近では、開封後どれくらいまでなら安心して食べられるか、表示の枠外に記載されていたり、ウェブサイトなどに掲載されている場合があります。気になる食品があれば、インターネットで調べてみたり、メーカーに問い合わせてみるのもおすすめです。
賞味期限を表示しなくてもよい食品があるって本当?
「あれ?このお砂糖、賞味期限表示がない!」なんて思ったことはありませんか?
実は、賞味期限の表示が義務付けられていない食品があります。例を挙げると、砂糖や塩、アイスクリーム類、チューイングガム、ペットボトル入りの清涼飲料水など。
これらは、品質の劣化が極めて少ないとされ、表示が免除されているのです。
もちろん、メーカーが自主的に期限を表示している場合もあります。
まとめ 食品の期限は健康な暮らしへのヒント
賞味期限が切れた食品を食べるか、廃棄するか。
その判断に迷ったとき、今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。
食品の期限について知ることは、あなた自身の健康を守るだけでなく、食品を無駄にしない工夫にもつながります。
正しい知識が、フードロス削減や持続可能な暮らしへの第一歩になるかもしれません。
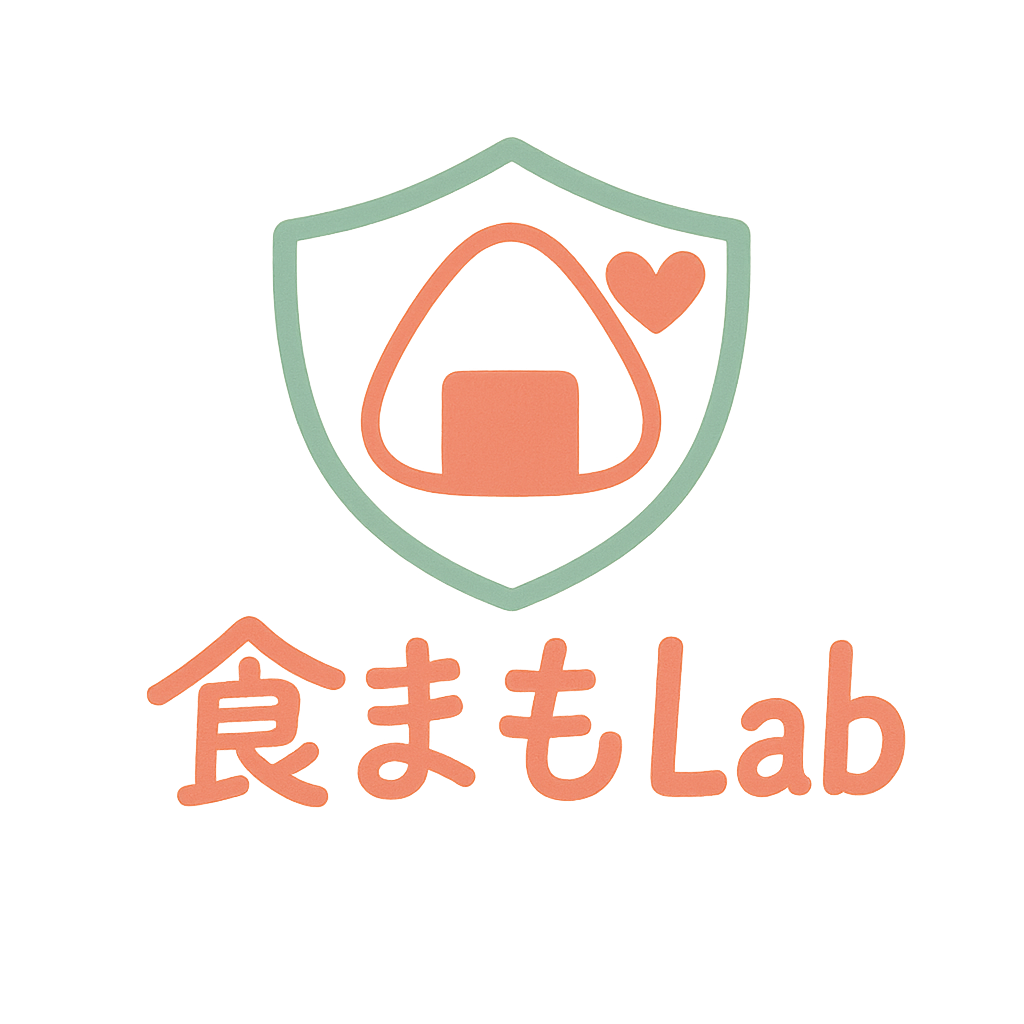
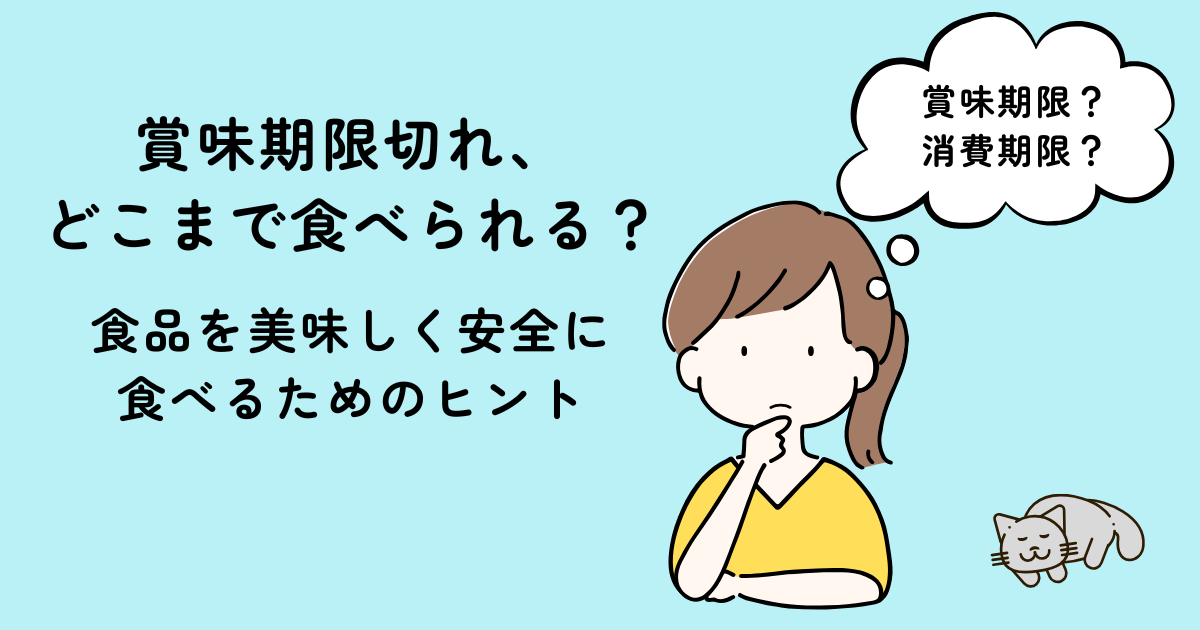
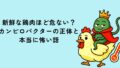

コメント