はじめに
カフェを開きたい、家庭で作ったお菓子を販売したい――そんな夢を実現するために避けて通れないのが「営業許可」です。
実は、飲食店や菓子販売を始めるには食品衛生法に基づく許可が必要で、これを知らずに準備を進めてしまうと、開業が大きく遅れてしまうこともあります。
この記事では、カフェや菓子販売を始めたい方に向けて、営業許可の基本知識から取得までの流れ、注意すべきポイントまでを 4ステップでやさしく解説 します。
営業許可とは?カフェや菓子販売でなぜ必要?
飲食店やお菓子を販売するには、食品衛生法第52条に基づき「営業許可」が必要です。
許可とは「本来禁止されている行為を、条件を満たした場合に認めること」。
つまり飲食物を調理・製造し、販売することは法律上禁止されており、営業許可を取ることで初めて認められるのです。
無許可で営業すると…
- 食品衛生法違反(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)
- お客様や取引先からの信用失墜
「知らなかった」では済まされません。必ず事前に許可を取りましょう。
カフェ・菓子販売で必要な営業許可の種類
飲食店営業許可(カフェ)
カフェやレストランなど、店内で飲食を提供する場合に必要です。
かつては「喫茶店営業」という許可がありましたが、現在は「飲食店営業」に一本化されています。
菓子製造業許可(お菓子の製造販売)
クッキーやケーキ、パンなどのお菓子を製造・販売する場合に必要です。
包装済みのお菓子を仕入れて販売するだけなら対象外ですが、ほとんどの場合はこの許可が必須となります。
届出が必要なケース
32業種の営業許可に該当しなくても「届出」が必要になる場合があります。
例:包装済みのケーキやパンを仕入れて販売する場合(長期保存できる食品を除く)
飲食店営業と菓子製造業の関係(2021年法改正のポイント)
- 「飲食店営業」の許可を受けた施設で作ったケーキを包装して販売する場合、調理提供している食品の持ち帰りの範囲内であれば、新たに「菓子製造業」の許可は不要です。
例:カフェで作ったケーキをそのままテイクアウト販売するケース - 「菓子製造業」の許可を受けた施設で作った菓子やパンに飲料を添えて提供する場合、新たに「飲食店営業」の許可は不要です。
例:焼き菓子工房で焼いたマフィンにコーヒーをつけて販売するケース
ただし、あくまで「主たる営業」がどちらかで、提供方法が付随する範囲で認められるものです。
販売形態が複雑な場合や境界があいまいな場合は、必ず管轄の保健所に確認しましょう。
家庭のキッチンでお菓子は販売できる?
よくある誤解が「家庭で作ったお菓子を販売していいのか?」という疑問です。
結論からいうと、家庭のキッチンで作ったお菓子は販売できません。
理由は、家庭のキッチンは営業許可の施設基準を満たしていないからです。
例えば・・・
- 調理場と住居部分の区分ができていない
- 手洗い専用の設備がない
その他にも施設基準が細かく定められていて、すべてを満たさなければなりません。
では、解決策はあるのでしょうか?
考えられる方法は以下のとおりです。
- 自宅の一角を基準に合わせて改装する
- シェアキッチン・レンタルキッチンを利用する
できそう!やってみたい!と思ったら次のステップに沿って進めていきましょう。
営業許可取得までの流れ
ステップ1|施設基準を知ろう
営業許可を得るには、まず施設が基準を満たしていることが必須です。
主な基準:
- 調理場と住居を区分
- 床・壁は清掃しやすい耐水性素材
- 手洗い器はシンクとは別に専用設置
👉 2021年の食品衛生法改正で、水栓に手を触れず止水できる構造(センサー式、レバー式、足踏み式など)が必須 になりました - シンクは2槽以上、お湯が出ること
- 十分な容量のある冷蔵庫を用意、温度計設置
- 食器や器具は扉付きの保管庫に
- トイレは専用手洗いを備え、作業場に影響しない位置に
他にも細かな施設基準があります。飲食店営業と菓子製造業でも異なる事項がありますし、保健所によって重視するポイントが異なることも。
最もハードルになるのは「手洗い器とシンクの増設」。工事が必要になるケースが多いので、早めに業者と相談しましょう。
ステップ2|保健所で事前相談
必ず開業予定地を管轄する保健所に相談します。工事の前に行かないとやり直しになることも。
準備するもの:
- 図面(縮尺付きで正確に)
- 食品衛生責任者の資格(調理師・栄養士・製菓衛生師など/なければ1日講習で取得可)
- 水質検査成績書(井戸水・貯水槽使用の場合)
ステップ3|設備・工事
事前相談の内容を反映して工事を進めます。
「とりあえず許可が下りればいい」ではなく、安全な食品を提供できる施設づくり を意識しましょう。
ステップ4|申請・検査
工事が完了する前に、必要書類をそろえて申請します。
- 手数料:飲食店営業 約18,000円、菓子製造業 約16,000円(自治体で差あり)
- 書類:申請書、平面図、責任者資格証、水質検査成績書(必要な場合)など
工事が完了したら、保健所職員が施設を検査し、問題がなければ許可証が交付されます。
保健所とのやり取りのコツ
- 作業動線や食材保管方法をシミュレーションして答えられるようにしておく
- 不明点はその場で確認。自己判断はNG
- 職員は敵ではなく、むしろ相談に乗ってくれるパートナー
許可取得後の注意点
- 許可証が届く前に営業開始するのはNG
- 有効期限は5〜8年、更新を忘れないこと
- 営業内容や設備を変更する場合は「変更届」や場合によっては再許可
- 廃業時は「廃止届」
- 2021年改正で、HACCPに沿った衛生管理が義務化され、記録も必要
まとめ
カフェや菓子販売を始めるには、必ず営業許可が必要です。
そのためには、施設基準の理解・保健所相談・工事・申請検査 の4ステップを順番に進めることが大切です。
家庭のキッチンそのままでは営業できませんが、シェアキッチンや改装で夢を実現する道はあります。
正しい手続きを踏めば、あなたのカフェやお菓子販売は安心してスタートできます。
お客様に「安全でおいしい」を届ける第一歩として、営業許可をしっかりクリアしていきましょう。
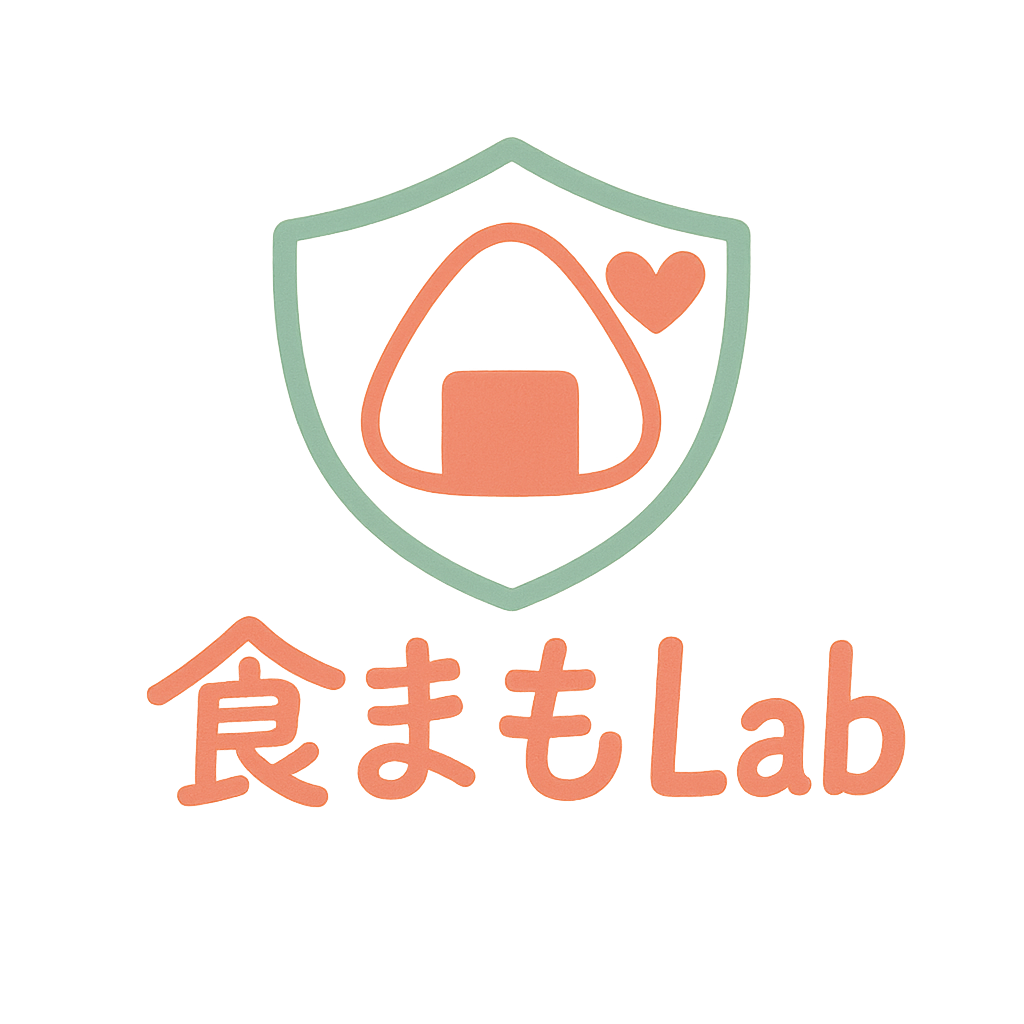


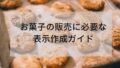
コメント